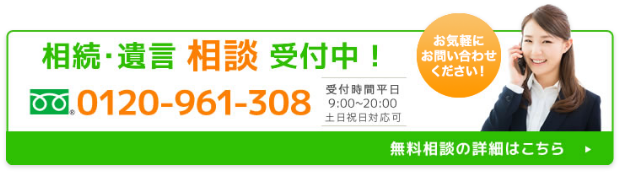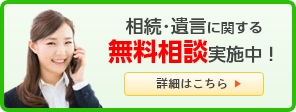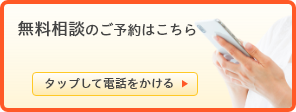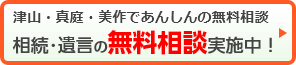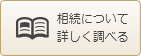2021年07月07日
Q:不動産を相続しました。司法書士の先生、名義変更の方法について教えてください。(美作)
先月美作に住む母が亡くなりました。
父はすでに亡くなっており、母は美作市内の不動産を複数もっており、相続人は私のみですので、私がそれらの不動産を相続する事になりました。
不動産に関しても相続に関しても初めての事ばかりで、何から手をつけたらいいかもわからない状況です。
まずは不動産の名義変更をしなければいけないかと思っているのですが、手続きはどのように進めたらいいか、教えていただけませんでしょうか。(美作)
A:相続による不動産の名義変更手続きについてご説明いたします。
相続が開始すると、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰になるか確認します。
相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分割方法の話し合いをします。
話し合いがまとまり、相続した財産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
その後、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続後、不動産をすぐに手放す予定の場合にも、名義変更手続きが必要となります。
名義変更手続きの流れは以下の通りです。
①登記申請書を作成する。
②名義変更の申請に必要な書類を整え、不動産の所在地を管轄する法務局に提出する。
【名義変更申請の際に添付する書類】
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
相続の手続きは手続きに相続以上に時間や労力が取られます。
また、相続人に未成年者や行方不明者がいる、相続放棄を考えているなど、専門的知識が必要となるケースもありますので、相続手続きにお困りの際には専門家へ一度相談することをおすすめします。
美作近辺にお住まいで相続に関するお悩みの方は、津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。
津山・岡山相続遺言相談室では豊富な知識と経験をもつ専門家が、津山、美作にお住まいの皆様の相続に関するお悩みを解決いたします。
美作の皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
相談事例を読む >>
2021年06月05日
Q:遺言書を確認したところ、遺言執行者に私の名前が書かれていました。司法書士の先生、遺言執行者は何をすることになるのでしょうか。(真庭)
司法書士の先生、困ったことになっているので助けてください。先日真庭市内にある病院で父が亡くなり、相続が発生しました。
生前父から真庭の公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、真庭の実家で葬式を済ませた後、私と母と妹の三人で遺言書を確認することにしました。
驚いたのは遺言書に書かれていた最後の文言です。「長女である〇〇を遺言執行者に指定する」と書かれていました。遺言執行者が何をする人なのかも分かりませんし、正直不安しかありません。遺言書の遺言執行者は何をすることになるのか教えてください。(真庭)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現するための行為を執行することです。
遺言執行者とはその言葉通り遺言を執行する方のことで、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有します。たとえば相続財産のなかに名義変更が必要な不動産などがあった場合、遺言執行者は相続人に代わって手続きを行います。つまり遺言執行者に指定されたご相談者様は、お父様の遺言書に書かれた遺言内容を実現するための相続手続きを一手に担うことになるというわけです。
なお遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、相続人はもちろんのこと、第三者でもなれます(未成年や破産者は除く)。遺言書において指定がなかった場合は相続人が相続手続きを進めることになりますが、利害関係人(相続人や受遺者、債権者)が申立てをすれば家庭裁判所が選任してくれます。相続人だけで遺言内容を実現するのは困難だと思われる煩雑な事務手続きが必要な場合は、遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。
ご相談者様のように予期せぬ形で遺言執行者に指定されたとなると、不安しかないのも無理はありません。
相続や遺言書のことでお困りの際はぜひ、真庭および真庭近郊にお住まいの皆様の相続や遺言書作成を多数サポートしてきた津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では真庭をはじめ真庭近郊にお住まいの皆様をメインに、経験豊富な専門家がお一人おひとりのお悩みに合わせて親切丁寧に対応いたします。
初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
相談事例を読む >>
2021年05月08日
Q:司法書士の先生にご質問です。自分たちだけで相続手続きをすることは可能ですか?(津山)
私は津山で一人暮らしをしている50代のサラリーマンです。津山は私の地元でして、両親も津山の実家で暮らしていますが、3年前に父が、半月前に母が亡くなりました。
財産としては津山の実家と津山市内のマンションがあり、私と弟が相続することになると思います。財産もそう多くないし借金もないようですので、弟と2人で相続手続きをしようと考えています。そこでふと気になったのですが、専門家の方でなくても相続手続きをすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(津山)
A:専門家でなくとも相続手続きを進めることは可能です。
結論から申しますと、相続手続きは専門家でなくとも進めることはできます。しかしながら、ご自分たちだけで相続手続きをする場合には、気をつけなければならない点があることも確かです。
たとえば、相続手続きとして最初に行うことになるのは法定相続人の確定です。
ご相談者様のお話ですと、財産を相続することになるのはご自分と弟様とのことですが、お母様の法定相続人となる方が本当にお二人だけなのかを証明する必要があります。
何故かというとお二人以外に法定相続人がいた場合、その方も含めたうえで遺産分割協議を行わなければ無効となってしまうからです。
相続手続きに際しては戸籍謄本を取得することになりますが、必要となるのはお母様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍謄本および相続人となる方の現在の戸籍謄本です。
お母様の戸籍謄本に関しては過去に戸籍を置いていた各自治体から取得することになるため、場合によっては相当な時間と手間がかかることを念頭に置いておきましょう。
このようにご自分たちだけで相続手続きをするとなると時間と手間がかかり、まとまった時間がとれない場合には「なかなか相続手続きが進まない…」といったことも考えられます。
相続手続きには期限が設けられていますので、期限内にきちんと完了できるよう、相続の開始とともに戸籍謄本の収集に取りかかりましょう。
相続というものは人生においてそう何度も経験することではありませんから、分からないことや不安に思うことがいくつもあるのは当然です。そんな時はぜひ津山・岡山相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>
2021年04月10日
Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないかどうか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(津山)
司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は津山で夫と二人暮らしをしている60代の主婦です。先日のことですが津山の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、津山市内の葬儀場で葬式を済ませました。
それから妹と一緒に津山の実家へと足を運び、遺品整理を始めていた時のことです。たんすの中から父が書いたと思われる封のされた遺言書が見つかりました。
父から財産があることは聞いていましたが内訳までは把握していなかったので、できれば開封して中身を確認したいと思っております。私と妹とで開封しても問題ないでしょうか?(津山)
A:お父様が自筆で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認が必要です。
今回、お父様がご自分で書かれたと思われる遺言書が見つかったとのことですが、この遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。
自筆証書遺言(以下遺言書)は、ご家族であっても勝手に開封することはできず、開封してしまうと5万円以下の過料を支払うことになります。遺言書を発見した場合はけして開封せず、まずは家庭裁判所で検認の申立てを行いましょう。
ただし2020年7月に施行された保管制度により、法務局に預けられていた自筆遺言証書に関しては検認手続きを行う必要はありません。
申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がきますので、それまでに事前提出をしてください。遺言書の内容は、相続人等の立会いのもと裁判官が遺言書を開封し検認を行うことではじめて確認できるようになります。
申立てを行った相続人以外は必ずしも検認期日に出席する必要はなく、相続人全員がそろっていなくても検認手続きは実行されるのでご安心ください。
なお、遺言書に検認済証明書が付いていないと遺言内容を執行することはできないため、検認済証明書の申請も忘れずに行いましょう。
ご相談者様のように、予期せぬ形で遺言書を発見してしまい、疑問や不安を覚えている方は多いかと思います。「誰に相談したらいいのかわからない」とお困りの場合は、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方を中心に、遺言書はもちろんのこと相続全般に関しても幅広くお手伝いさせていただいております。
初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げます。
相談事例を読む >>
2021年04月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続手続きをするために亡くなった父の財産を調べていますが、通帳とカードが見当たらず困っています。(津山)
司法書士の先生、はじめまして。私は二人の子どもを持つ津山在住の主婦です。実家も同じ津山にあるのですが、そこで母と仲睦まじく暮らしていた父が先日亡くなりました。
葬式は津山の実家で済ませ、家族みんなが落ち着いたころを見計らって相続手続きを始めようと思い、父の財産を調べているところです。
生前、退職金がまるまる入った口座があることを父から聞いていましたが、その通帳とカードがいくら探しても見当たりません。問い合わせをしようにも預けてある銀行名がわかりませんし、まさに八方ふさがりといった状況です。
相続人になる母と私が父の口座の存在を調べることはできますか?(津山)
A:ご相談者様が相続人であると証明する戸籍謄本を提出すれば、お父様の口座の存在を調査することは可能です。
結論から申しますと、相続人は亡くなった方の口座情報の開示を請求できるので、通帳やカードがなくてもお父様の口座の存在を調査することはできます。 ただ、お父様がご自分の財産の相続について終活ノートに等しいものなど、何らかの形で残している場合もありますので、まずはそれらがあるかどうかを改めて探してみてください。 仮にそれらが見つからなかった場合は、以下の方法で銀行名を特定しましょう。
①再度通帳・キャッシュカードを捜索
②ご実家やお父様が勤めていた会社近辺の銀行へ直接お問い合わせ
お父様宛の郵便物や実家のカレンダー、タオルなどを調べてみることで銀行名を特定できる可能性もあります。
なお、①②ともにお父様の口座の情報開示にはお父様とご相談者様の続柄が確認できる戸籍謄本の提出が必要ですので、あらかじめ用意しておくと請求手続きがスムーズです。
ご相談者のようにご家族だけで財産調査を行うとなると、時間や手間がかかったり予期せぬ問題が発生したりと、なかなか相続手続きが終わらないといったケースもあります。
津山近郊にお住まいで相続に関するお悩みごとのある方は、初回無料相談を実施している津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお問い合わせください。
津山・岡山相続遺言相談室では豊富な知識と経験をもつ専門家が、津山にお住まいの皆様の相続に関するお悩みを解決いたします。生前対策や遺言書作成につきましても全力でサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
相談事例を読む >>