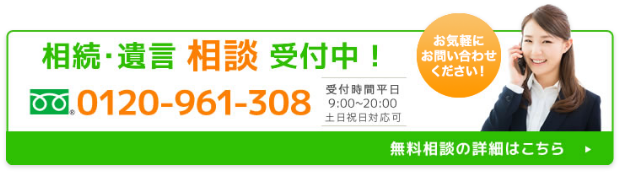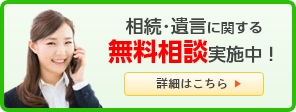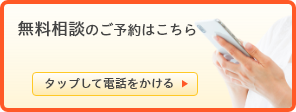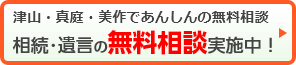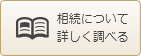2025年10月02日
Q:母の銀行通帳やキャッシュカードが見つからず相続手続きが中断しているので、司法書士の先生に助けて欲しいです。(美作)
先日、美作の実家で暮らしていた母が急に亡くなり、美作市内で葬儀を執り行いました。あまりに急だったもので気持ちも追いつかない状態ではあったものの、相続手続きに関しても早めに手続きをしようと妹と話しておりました。そんな中、美作の実家で家財整理をしつつ母の銀行通帳やキャッシュカードなども探しておりましたが、一向に見つかりません。母は倹約家で、長く営業職で勤めていた会社の退職金も手付かずであるという話も先日聞いたばかりです。しっかり者だった母が間違って捨ててしまうという事も考えられません…。せめてどこの銀行なのか分かれば良いのですが。こういった場合、私たちはどうしたら良いでしょうか。(美作)
A:相続人であれば銀行から残高証明書の取り寄せが可能です。戸籍謄本を用意しましょう。
津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。通帳やキャッシュカードが見当たらずお困りであるというお話ですが、亡くなったお母様が終活ノートや遺言を用意されていないかを今一度確認して下さい。亡くなった方の財産を全てご家族が把握している事が理想ではありますが、現実では難しいものです。終活ノートやメモから手がかりが見つかった場合には、まずご自身が相続人である証明のために戸籍謄本をご用意いただきます。そして、手がかりで該当した銀行や金融機関に対し、口座の取引履歴や残高証明などの情報開示を請求することが可能です。
もし、遺言や終活ノート、メモ等が全くないという場合においては、生活している場所からヒントを探しましょう。カレンダーやノベルティ、郵便物などからヒントが掴めたら、その銀行に問い合わせてみましょう。何も手がかりが掴めない場合には、お母様の生活圏にある美作の実家近くや職場近くの銀行に、こちらから直接問い合わせをしてみましょう。
その際には前述でもご説明した通り、ご自身が名義人であるお母様の相続人であるという証明に求められる戸籍謄本の準備が必須です。
相続手続きは聞きなれない言葉や用意した事がない書類を扱い、面倒や負担も多い手続きなので、ご不安やご心配な場合が多いかと思います。そんな時は相続の専門家である津山・岡山相続遺言相談室までご相談ください。相続手続き完了まできめ細やかにサポートを行います。
美作にお住まい、もしくは美作で相続専門家をお探しの皆様はぜひ、津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。津山・岡山相続遺言相談室では初回の無料相談をご用意しておりますので、ご相談をするかお悩みの方もぜひお気軽にご利用ください。美作の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>
2025年09月02日
Q:不動産を相続したら相続登記の申請が必要だと聞きました。司法書士の先生、申請の流れを教えてください。(真庭)
真庭で暮らしていた母が亡くなりました。現在家族で協力して遺品整理をしながら、相続についてどうするか考えているところです。
真庭の実家は父の名義なので今回の母の相続では関係してきませんが、母には祖父から相続した土地が真庭にあります。真庭の土地は今後活用する予定もないので、これを機に売却しようかと考えていたのですが、同じく真庭に住む母方の伯父から「土地を売却するにはまず相続登記の申請が必要なはずだ」と聞きました。手続きを後回しにすると厄介だから早めに済ませておけと助言を受けたので、まずは相続登記の申請の流れを知りたいと思い、今回ご相談させていただきました。(真庭)
A:相続した不動産の名義変更手続きともいえる相続登記の申請についてご説明します。
故人(以下、被相続人)が土地などの不動産を所有していた場合、その不動産の所有権が、相続人など別の人に移ったこと(所有権が移転したこと)を登記申請する必要があります。不動産の所有者が亡くなることにより行う所有権移転の登記を「相続登記」といい、簡単にいうと不動産の名義変更手続きのようなものです。
相続登記の申請が完了すれば第三者に対して主張(対抗)することが可能となります。相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されており、原則として相続の開始から3年以内に相続登記申請を行わなかった場合は過料の対象となりますので、相続登記の申請はお早めに行うことをおすすめしております。
■相続登記申請までの主な流れ(遺言書の無い場合)
(1)遺産分割協議を相続人全員で実施し、各財産の取得者を決め、協議結果を遺産分割協議書として文書化しましょう。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
(2)相続登記申請に必要な書類を準備します。主に必要となるのは以下のような書類ですが、相続状況によって必要書類は異なってきますのでご注意ください。
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 対象不動産を取得する人の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- (1)で作成した遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続関係説明図 など
(3)登記申請書を作成します。
(4)対象不動産の住所地を所轄する法務局(支局・出張所)へ登記申請書および必要書類を提出します。
以上が登記申請の流れです。相続登記の申請は司法書士が代行することも可能ですので、ご自身での手続きに不安があるときはぜひ津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。
特に、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合は家庭裁判所での手続きも必要となりますが、津山・岡山相続遺言相談室へご依頼いただければ、関連するさまざまな手続きも丸ごと対応させていただきます。
相続に精通した司法書士事務所として、真庭の皆様が行うべき相続手続きをトータルでサポートさせていただきますので、真庭で相続手続きが必要となった方はぜひ津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。
相談事例を読む >>
2025年08月04日
Q:父が亡くなりました。相続人である母が認知症の場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生に教えていただきたいです。(津山)
津山に住む父が亡くなりました。父の相続財産は津山の自宅と預貯金が1,000万円ほどです。相続人は、私と母と妹の3人になります。母は数年前から重度の認知症を患っております。自分で署名や押印など、相続手続きに必要な行為はできない状態です。そのため、相続手続きを進められずにいます。このような場合、相続手続きを進める方法はありますか?母に代わって署名等を行い進めてしまってもよいのでしょうか?(津山)
A:相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。
正当な代理権がないご家族が、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名や押印などの行為をするのは違法です。相続人に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度は、認知症や障害などによって意思能力が不十分な方を保護する制度です。認知症によって判断能力が不十分な場合、遺産分割などの法律行為はできません。
この場合、認知症の方の成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行うことで成年後見人が選任されます。選任された成年後見人は、認知症の方の代理人として遺産分割などの法律行為が可能になります。
成年後見人は、親族が選任されることもあれば、専門家などの第三者がなる場合もあります。また、1人ではなく複数人が選任されることもあります。
なお、成年後見人は下記に該当する者はなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人が選任された後は、遺産分割協議後も制度の利用が続きます。したがって、先を見据えてご本人にとってのベストを考慮した上で法定後見制度を利用するようにしましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でご相談いただけます。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、手続きが複雑になりますので専門家へと相談をすることをおすすめします。
津山在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。
相談事例を読む >>