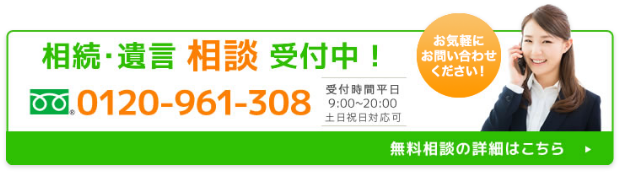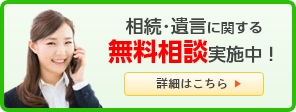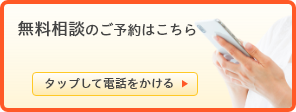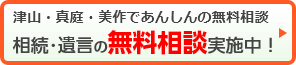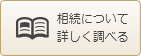2022年12月02日
Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(美作)
私は50代の会社員です。美作の実家に暮らしていた母が亡くなり、現在相続の手続きを進めています。父はすでに他界しており、私が相続する遺産は美作の実家と預金くらいです。今は実家から離れて暮らしており、仕事もありますので、夏季休暇などでの帰省時に相続手続きを済ませることができたらと考えております。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(美作)
A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、ご自宅の建物や土地などの不動産と、現金や預金・株などの金融資産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは不動産の手続きですが、被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
また、金融資産のお手続きについては、被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。
その他、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合などには、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。
美作にご実家のある方、美作にお住まいの家族が亡くなられた方の相続手続きはぜひ津山・岡山相続遺言相談室をご利用下さい。地域密着の専門家が丁寧に対応させて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。
相談事例を読む >>
2022年10月04日
Q:父の遺言書に母の署名もされていることがわかりました。連名のような内容になっていますが、これは遺言書として正しいものなのでしょうか。司法書士の先生にお話を伺いたいです。(美作)
美作市内の病院で闘病をつづけていた父が亡くなりました。生前に遺言書を残したという話は聞いていたので、母親と自宅の片付けをしながら遺言書の話をしていたところ、母もその遺言書に署名をしたと言い出しました。父の部屋にあった遺言書はまだ封がしてあり中は確認していないのですが、内容は父所有の美作市内の不動産と預金の分割方法についての記載あるとのことでした。2人で作ったといっているので、専門家の先生に相談をして作成したものではなさそうです。連名の遺言書というものを聞いたことがありませんので、この遺言書がそもそも法的な効力を持つのかどうかも不明です。この遺言書の取り扱いについて司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(美作)
A:婚姻関係のあるご夫婦であっても、2名以上の署名がされた遺言書は無効です。
民法上、今回のケースは2名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ですから、婚姻関係にあるご夫婦であっても残念ながら今回のケースではお父様の遺言書は無効な内容と判断されます。
遺言書の特性として、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」とされるため、複数の遺言者がいた場合そのうちの誰かが主導的立場にたち作成した可能性も否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていない、と判断がされることになります。
また、遺言書の撤回という面においても連名では自由が奪われてしまうことになります。遺言書は、遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名である場合はそれぞれの同意がなければ撤回ができず、それは遺言者の意志を自由に反映させることになりません。これでは、個人の最終意志となる大事な証書に自由な意思が反映されず、遺言の意味を成しません。
そして、法律により定められている形式に沿って作成されていない遺言書も原則無効となりますので、自筆での遺言書を検討さてる方はご注意ください。
ご自身のタイミングで自由に作成することができるのが「自筆証書遺言」です。費用も手間もかからずに作成できますが、専門家への相談もいらずに手軽にできることにより法的に無効な内容になっている可能性がある、というデメリットがあります。もし、今後ご相談者様も遺言書を残そうとお考えでしたら、相続や遺言書に関する専門家の先生へと相談されることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では、美作にお住いのみなさまの相続の専門家として、相続手続きから遺言書の作成まで幅広く日々お手伝いをさせて頂いております。美作にお住いの皆様、ぜひ相続に関してお困りごとがございましたら、当相談室の無料相談をご利用ください。ご相談者様の最善策を専門家がご提案をさせて頂きます。
相談事例を読む >>
2022年07月01日
Q:私の相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのかを司法書士の先生にお伺いしたいです。(美作)
司法書士の先生、はじめまして。相続のことでご相談させてください。
私は美作のマンションで内縁関係にある女性と暮らしているのですが、半月前に大きく体調を崩したこともあり、自分の財産について色々と考えるようになりました。
もちろん、私にもしものことがあった場合には全財産を一緒に暮らしている女性に渡すつもりでいますが、気になっているのが別れた妻の存在です。
私の財産が別れた妻に渡るような事態だけは何としても避けたいのですが、相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのでしょうか?
ちなみに、内縁関係にある女性、別れた妻ともに子供はもうけていません。(美作)
A:別れた奥様はご相談者様の相続人には該当しません。
被相続人の配偶者として相続人になれるのは、法律上の婚姻関係にある方です。よって別れた奥様はご相談者様の相続人には該当しないため、所有している財産が渡ることはないのでどうぞご安心ください。
また、内縁関係にある女性に全財産を渡すつもりでいるとのことですが、今のままですとその方にご相談者様の財産を受け取る権利はありません。遺言書を作成すれば「遺贈」という形で財産を渡すことが可能ですので、生前のうちにきちんと対策を講じておきましょう。
相続が発生した際に被相続人の法定相続人となる者の順位は以下の通りです。
- 第一順位:被相続人の子供または孫(直系卑属)
- 第二順位:被相続人の父母または祖父母(直系尊属)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に法定相続人となり、他の相続人と共同で財産を承継します。
ご相談者様にはお子様はいらっしゃらないとのことですので、ご自身の相続が発生した場合、ご存命であれば父母または祖父母が法定相続人となります。
父母と祖父母には最低限受け取ることができる財産の割合を定めた「遺留分」が認められているため、内縁関係にある女性に全財産を渡す旨を記した遺言書を残してしまうと両者間で揉める可能性があります。
円満な相続を希望されるようであれば相続を得意とする専門家に一度、相談してみることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では相続・遺言書作成に精通した司法書士による初回無料相談を設け、美作の皆様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事について詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
美作の皆様からのお問い合わせを津山・岡山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>